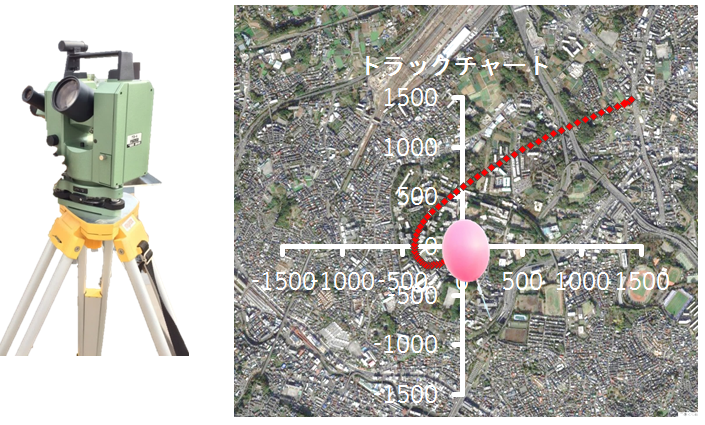 図2-1 セオドライトによる追尾
①雲画像の撮影
図2-1 セオドライトによる追尾
①雲画像の撮影

 図2-1 動画撮影
②PIVでの定量的な雲の移動の検出
図2-1 動画撮影
②PIVでの定量的な雲の移動の検出
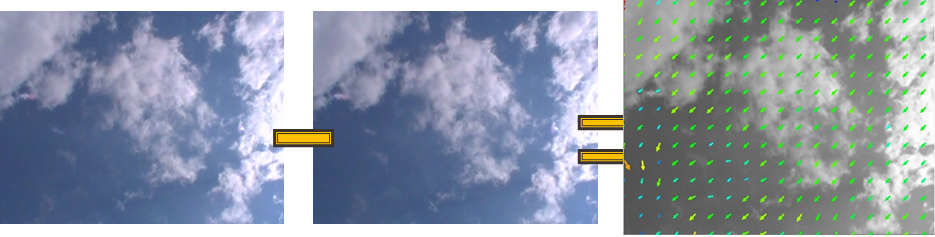 図2—2 PIV結果
③雲風の算出
3) 結果
観測は2016年11月29日から2017年9月14日の全19回行った。
しかし動画撮影が上手く行えていなかった4回分を除いた15回分で検証していく。
以下の図3-1に観測日時とその日の雲量と雲の種類を記す。
図2—2 PIV結果
③雲風の算出
3) 結果
観測は2016年11月29日から2017年9月14日の全19回行った。
しかし動画撮影が上手く行えていなかった4回分を除いた15回分で検証していく。
以下の図3-1に観測日時とその日の雲量と雲の種類を記す。
 図3-1 観測日時とその日の雲量と雲の種類
ここで、2016年12月7日の結果を見ていく。
まず、得られた画像をPIVにかけ、標準偏差÷平均をしたものをばらつきと定義した。
その評価基準は、0<ばらつき<50%を○、50<ばらつき<100%を△、100%<ばらつきを✖とした。
この日のばらつきは図3-2のように19.8%であったため、評価は○となる。
図3-1 観測日時とその日の雲量と雲の種類
ここで、2016年12月7日の結果を見ていく。
まず、得られた画像をPIVにかけ、標準偏差÷平均をしたものをばらつきと定義した。
その評価基準は、0<ばらつき<50%を○、50<ばらつき<100%を△、100%<ばらつきを✖とした。
この日のばらつきは図3-2のように19.8%であったため、評価は○となる。
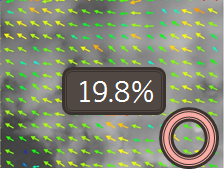 図3-2 2016年12月7日のPIV結果とばらつき
風向についても観点を設けた。
0<風向<45°を○、45<風向<90°を△、90°<風向を×とした。
図3-2 2016年12月7日のPIV結果とばらつき
風向についても観点を設けた。
0<風向<45°を○、45<風向<90°を△、90°<風向を×とした。
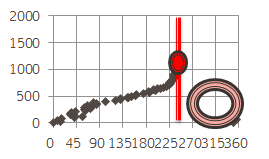 図3-3 2016年12月7日の風向の結果
風速は0<風速<1.0m/sを○、1.0<風速<2.0m/sを△、2.0m/s<風速を×とした。
図3-3 2016年12月7日の風向の結果
風速は0<風速<1.0m/sを○、1.0<風速<2.0m/sを△、2.0m/s<風速を×とした。
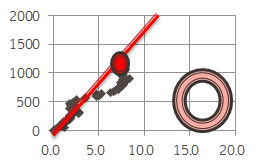 図3-4 2016年12月7日の風速の結果
このように、全ての観測事例に対して同様に検証を進めると、それぞれ以下の結果になった。
評価は左から順にばらつき、風向、風速を示す。
図3-4 2016年12月7日の風速の結果
このように、全ての観測事例に対して同様に検証を進めると、それぞれ以下の結果になった。
評価は左から順にばらつき、風向、風速を示す。
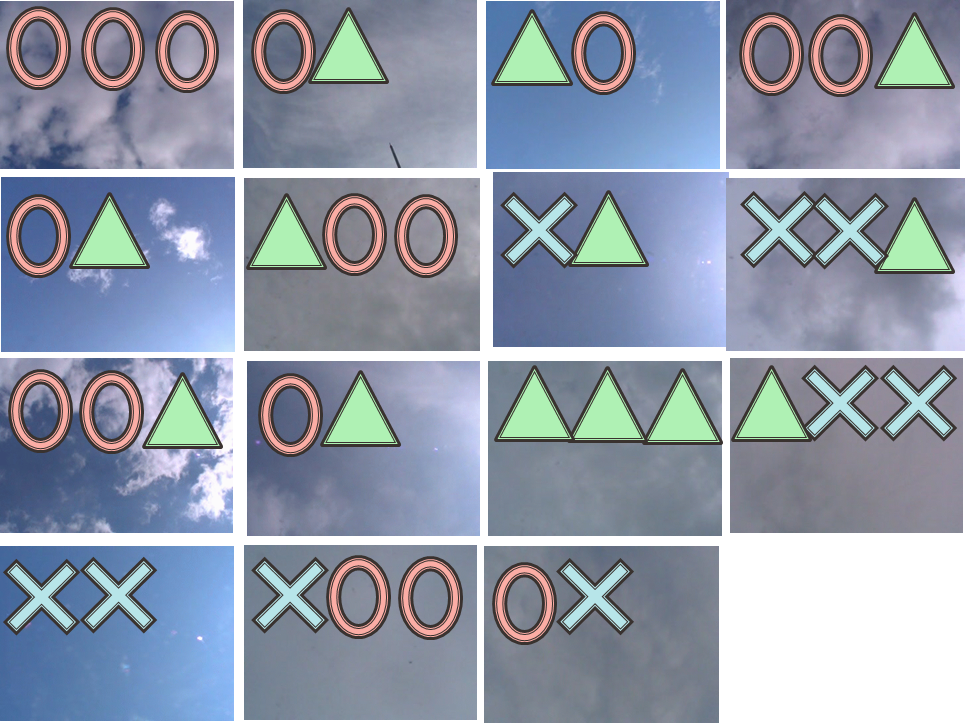 図3-5 全事例の結果
4) 考察
これらの結果が、雲量と雲の種類に依存していると考えた。
こちらが雲量とばらつきの関係を示したものである。
雲量が4~7のとき、ばらつきが50%を下回ることが多いことがわかる。
図3-5 全事例の結果
4) 考察
これらの結果が、雲量と雲の種類に依存していると考えた。
こちらが雲量とばらつきの関係を示したものである。
雲量が4~7のとき、ばらつきが50%を下回ることが多いことがわかる。
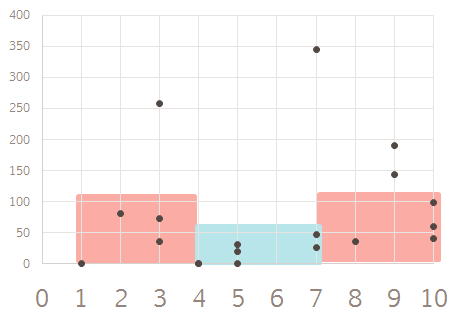 図4-1 雲量とばらつきの関係
また、雲の種類とばらつきについても注目してみた。
観測回数の多かった、積雲、乱層雲、巻層雲では、積雲が観測された場合、
ばらつきが100%未満が多い。
図4-1 雲量とばらつきの関係
また、雲の種類とばらつきについても注目してみた。
観測回数の多かった、積雲、乱層雲、巻層雲では、積雲が観測された場合、
ばらつきが100%未満が多い。
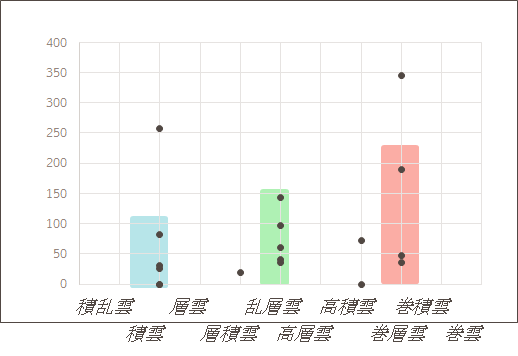 図4-2 雲の種類とばらつきの関係
5) まとめ
積雲で、雲量が4~7のとき、雲風は良い結果を得られることがわかった。
今後は実際に学校現場で観測を行った際、生徒がどれほど興味を抱くか検証したい。
図4-2 雲の種類とばらつきの関係
5) まとめ
積雲で、雲量が4~7のとき、雲風は良い結果を得られることがわかった。
今後は実際に学校現場で観測を行った際、生徒がどれほど興味を抱くか検証したい。
2018/03/21 中村