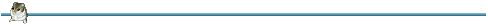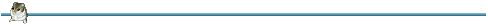
Road to 婥徾梊曬巑
儅僢僗儖摴応偺栧壓惗傗TeamSORA婥徾梊曬巑偵傛傞
梊曬巑偵側傞傑偱偺丄
摴偺傝傗嶲峫彂傪婰榐偡傞丅
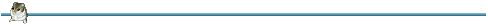 偒偭偐偗
暋崌婥徾妛尋媶幒(媑揷尋媶幒)傊嶲壛偡傞偙偲傪偒偭偐偗偵婥徾妛偵偮偄偰妛傏偆偲巚偄傑偟偨丅壗傪妛傋偽傛偄偐傢偐傜側偐偭偨偨傔丄婥徾梊曬巑傪栚巜偡偙偲偵偟傑偟偨丅婥徾梊曬巑偺崌奿棪偑掅偄偙偲偼抦偭偰偄偨偺偱丄崌奿偡傟偽戝偒側帺怣偵側傞偲巚偄丄偦偺偙偲偑杮奿揑偵栚巜偡屻墴偟偲側傝傑偟偨丅
偒偭偐偗
暋崌婥徾妛尋媶幒(媑揷尋媶幒)傊嶲壛偡傞偙偲傪偒偭偐偗偵婥徾妛偵偮偄偰妛傏偆偲巚偄傑偟偨丅壗傪妛傋偽傛偄偐傢偐傜側偐偭偨偨傔丄婥徾梊曬巑傪栚巜偡偙偲偵偟傑偟偨丅婥徾梊曬巑偺崌奿棪偑掅偄偙偲偼抦偭偰偄偨偺偱丄崌奿偡傟偽戝偒側帺怣偵側傞偲巚偄丄偦偺偙偲偑杮奿揑偵栚巜偡屻墴偟偲側傝傑偟偨丅
摴偺傝
2024擭3寧丂帋尡曌嫮奐巒
2025擭1寧丂庴尡(堦斒乑丄愱栧乑丄幚媄庴偗偢)
2025擭8寧丂庴尡(崌奿)
2025擭10寧丂婥徾梊曬巑帒奿庢摼
0.帋尡曌嫮
堦斒抦幆偲愱栧抦幆偼乽撉傫偱僗僢僉儕! 婥徾梊曬巑帋尡 崌奿僥僉僗僩 戞2斉
乿偲乽婥徾梊曬巑帋尡惛慖栤戣廤乿丄幚媄偼乽僀儔僗僩恾夝 傛偔傢偐傞婥徾妛亂幚媄曇亃乿偲夁嫀栤偱曌嫮傪偟傑偟偨丅妛壢偼柶彍偑偁傞偙偲傪抦偭偰偄偨偺偱丄偼偠傔偵妛壢偺崌奿傪栚巜偟傑偟偨丅
乑妛壢帋尡
妛廗丗
妛壢偺嶲峫彂傪2廃撉傫偱偍偍傛偦棟夝偟丄帋尡3偐寧慜偐傜栤戣墘廗傪巒傔傑偟偨丅嵟弶偼傎偲傫偳夝偗傑偣傫偱偟偨偑丄娫堘偊偨栤戣偲偦偺扨尦偺暅廗傪孞傝曉偡偙偲偱彮偟偢偮夝偗傞傛偆偵側傝傑偟偨丅
堦斒抦幆丗
朄棩偺栤戣偼栤戣悢偑懡偔偰廳梫偱偁傞偙偲偼抦偭偰偄偨偺偱偡偑丄偳偆偟偰傕妎偊傜傟側偐偭偨偨傔丄懠偺扨尦傗寁嶼栤戣傪棊偲偝側偄傛偆偵偟偰朄棩偺栤戣偼塣偵擟偣傑偟偨丅塣偑椙偔偰僊儕僊儕庴偐傝傑偟偨丅
愱栧抦幆丗
塹惎夋憸偺栤戣丄杊嵭偵娭偡傞栤戣偑嬯庤偱偟偨丅偁傑傝妎偊偰偄傑偣傫偑丄塹惎夋憸偺栤戣偼杮斣偱傕娫堘偊偨婥偑偟傑偡丅杊嵭偵娭偡傞栤戣偼丄岾塣側偙偲偵捈慜偵夝偄偨栤戣偺椶戣偑偱偨偨傔夝偔偙偲偑偱偒傑偟偨丅偦偺1揰偑崌奿偵偮側偑傝傑偟偨丅
乑幚媄帋尡
妛廗丗
帋尡偺3偐寧慜偐傜幚媄偺曌嫮傪巒傔傑偟偨丅嶲峫彂傪撉傒恑傔偰丄怴偨偵妎偊傞偙偲偼彮側偄偙偲偵婥偑晅偄偨偨傔丄夁嫀栤傪夝偒側偑傜妎偊偰偄偔偙偲偵偟傑偟偨丅偙偺偲偒偵揤婥恾偵懳偟偰傎偲傫偳掞峈偑偁傝傑偣傫偱偟偨丅偙傟偼儅僢僗儖摴応偺揤婥恾夝愅偑戝偒側椡偵側偭偨偲妋怣偟偰偄傑偡丅巒傔偺偆偪偼悢擔偵夁嫀栤1偮偔傜偄偺儁乕僗偱曌嫮傪偟偰偄傑偟偨偑丄2廡娫慜偵徟傝偼偠傔丄堦擔偵1夞暘偺夁嫀栤墘廗傪峴偄傑偟偨丅崌寁12夞暘偔傜偄夝偒傑偟偨丅杮摉偼夝偒側偍偟傪偟偨曽偑椙偄偲偼巚偄傑偡偑丄帪娫偑側偔偰偱偒傑偣傫偱偟偨丅
嬯愴偟偨偙偲丗
帺暘偺孹岦偲偟偰丄儈僗偼彮側偄戙傢傝偵帪娫偑懌傝側偄偙偲偑懡偐偭偨偱偡丅墘廗偺嵺偵偼儁乕僗傪忋偘傞偙偲傪堄幆偟偰偄傑偟偨偑丄帋尡慜擔偱傕夝偒愗傞偙偲偼弌棃側偐偭偨偨傔丄夝偒愗傞偙偲偼偁偒傜傔傑偟偨丅杮斣傕幚媄1偲2偱偦傟偧傟栺10揰暘偼嬻棑偺傑傑弌偟傑偟偨丅
丂栤戣偺嶌幰偑壗傪暦偙偆偲偟偰偄傞偺偐傪棟夝偱偒傞傛偆偵側傞傑偱偵偐側傝帪娫偑偐偐傝傑偟偨丅夁嫀栤傪傂偨偡傜夝偄偰偄偨傜彮偟偢偮棟夝偱偒傞傛偆偵側傝傑偟偨丅
傆傝偐偊偭偰
丂崌奿偱偒偨偺偼塣偺偍偐偘偩側偭偰巚偄傑偡丅偟偐偟丄崌奿偱偒偨偙偲偼戝偒側帺怣偵側傝傑偟偨丅帋尡曌嫮偼偁傑傝岲偒偠傖側偄偺偱偡偑丄婥徾梊曬巑帋尡偼尋媶偵傕偮側偑傞懠丄堦弿偵栚巜偡拠娫偑偄偨偨傔妝偟偔曌嫮偱偒傑偟偨丅庴偗偰傛偐偭偨側偲巚偄傑偡丅嵟屻偵丄榓揷偝傫偵姶幱傪揱偊偨偄偱偡丅儅僢僗儖摴応偺揤婥恾夝愅偑崌奿偵偮側偑偭偨偲傂偟傂偟偲姶偠偰偄傑偡丅
2025擭12寧UP
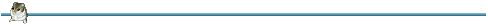 偒偭偐偗
丂WWF僕儍僷儞偺僕儏僯傾夛堳偲偟偰妶摦偡傞拞偱丄婥岓曄摦偺塭嬁偵傛傝條乆側栰惗惗暔偑愨柵偺婋婡偵昺偟偰偄傞尰忬偵偮偄偰抦偭偨傝丄抧媴壏抔壔偵傛傝寖恟壔偟偨戝塉丒峖悈側偳偺旐奞忬嫷傪儊僨傿傾偱栚偵偟偨傝偟偨偙偲偱丄娐嫬栤戣偵敊慠偲偟偨娭怱偑偁傝傑偟偨丅偦偺偨傔丄戝妛偱偼娐嫬妛傪峀偔妛傇偙偲偑偱偒傞妛壢偵恑妛偟傑偟偨丅偦偟偰丄戝妛1擭師 (2021擭) 偵曻憲偝傟偨楢懕僥儗價彫愢乽偍偐偊傝儌僱乿傪帇挳偟偰婥徾妛偵娭怱傪傕偪丄傑偨僸儘僀儞偑婥徾梊曬巑偲偟偰幮夛偵峷專偡傞巔偵姶柫傪庴偗偨偨傔丄帺恎傕帋尡傪庴偗偰傒偨偄偲峫偊傞傛偆偵側傝傑偟偨丅崌奿棪偑旕忢偵掅偄帋尡偲偄偆偙偲傕丄帺恎偺幚椡傪帋偟偰傒偨偄偲偄偆儌僠儀乕僔儑儞偺尮偱偟偨丅
偒偭偐偗
丂WWF僕儍僷儞偺僕儏僯傾夛堳偲偟偰妶摦偡傞拞偱丄婥岓曄摦偺塭嬁偵傛傝條乆側栰惗惗暔偑愨柵偺婋婡偵昺偟偰偄傞尰忬偵偮偄偰抦偭偨傝丄抧媴壏抔壔偵傛傝寖恟壔偟偨戝塉丒峖悈側偳偺旐奞忬嫷傪儊僨傿傾偱栚偵偟偨傝偟偨偙偲偱丄娐嫬栤戣偵敊慠偲偟偨娭怱偑偁傝傑偟偨丅偦偺偨傔丄戝妛偱偼娐嫬妛傪峀偔妛傇偙偲偑偱偒傞妛壢偵恑妛偟傑偟偨丅偦偟偰丄戝妛1擭師 (2021擭) 偵曻憲偝傟偨楢懕僥儗價彫愢乽偍偐偊傝儌僱乿傪帇挳偟偰婥徾妛偵娭怱傪傕偪丄傑偨僸儘僀儞偑婥徾梊曬巑偲偟偰幮夛偵峷專偡傞巔偵姶柫傪庴偗偨偨傔丄帺恎傕帋尡傪庴偗偰傒偨偄偲峫偊傞傛偆偵側傝傑偟偨丅崌奿棪偑旕忢偵掅偄帋尡偲偄偆偙偲傕丄帺恎偺幚椡傪帋偟偰傒偨偄偲偄偆儌僠儀乕僔儑儞偺尮偱偟偨丅
摴偺傝
2023擭1寧丂59夞庴尡 (堦斒亊丄愱栧亊丄幚媄庴偗偢)
2023擭8寧丂60夞庴尡 (堦斒亊丄愱栧亊丄幚媄庴偗偢)
2024擭8寧丂62夞庴尡 (堦斒乑丄愱栧乑丄幚媄庴偗偢)
2025擭1寧丂63夞庴尡 (妛壢柶彍丄幚媄亊)
2025擭8寧丂64夞庴尡 (妛壢柶彍丄幚媄乑)
2025擭10寧丂婥徾梊曬巑帒奿庢摼
0. 庴尡慜
U-CAN偺婥徾梊曬巑島嵗偵搊榐偟丄僥僉僗僩傪擖庤偟傑偟偨丅巗斕偺乽撉傫偱僗僢僉儕両婥徾梊曬巑帋尡崌奿僥僉僗僩乿傕峸擖偟傑偟偨偑丄寢嬊巊梡偟傑偣傫偱偟偨丅
1. 59夞
惃偄偱庴尡傪寛傔偨偼椙偄傕偺偺丄戝妛偺庼嬈傗晹妶摦丄傾儖僶僀僩側偳擔乆偺惗妶偵捛傢傟丄曌嫮偺儌僠儀乕僔儑儞偼壓偑傞堦曽偱偟偨丅偦偺偨傔丄偲傝偁偊偢庴尡偟偰傒偰帋尡偺宍幃偵偮偄偰抦傠偆偲偄偆寉偄婥帩偪偱丄偁傢傛偔偽妛壢堦斒偵崌奿偟偨偄偲峫偊偰偄傑偟偨丅U-CAN偺僥僉僗僩 (妛壢堦斒偺1嶜暘) 傪2丄3廃撉傒崬傒丄夁嫀栤傕夝偐偢偵帋尡偵椪傒傑偟偨丅寢壥偼埬偺忋嶶乆偱丄尰幚偼偦偆娒偔側偄偲抦傝傑偟偨丅
2. 60夞
59夞偺寢壥傪摜傑偊丄傕偭偲偟偭偐傝曌嫮偡傞昁梫偑偁傞偙偲偼暘偐偭偰偄偨傕偺偺丄傗偼傝帋尡僊儕僊儕傑偱曌嫮傪巒傔傜傟傑偣傫偱偟偨丅U-CAN偺僥僉僗僩 (妛壢堦斒丒愱栧偺2嶜暘) 傪2丄3廃撉傒崬傒丄夁嫀栤偼5夞暘傪1廃偟傑偟偨偑丄抦幆偺掕拝搙偼憡曄傢傜偢掅偐偭偨偱偡丅慜夞傛傝彮偟曌嫮偟偨暘丄棊偪偰偟傑偭偨偙偲偑偲偰傕夨偟偔丄偦傟偑62夞埲崀偺庴尡傊偺儌僠儀乕僔儑儞偵宷偑傝傑偟偨丅
3. 62夞
60夞偺寢壥傪摜傑偊丄1偐傜抦幆傪擖傟捈偡昁梫偑偁傞偲峫偊丄61夞偺帋尡偼僗僉僢僾偟傑偟偨丅敿擭傎偳偐偗偰U-CAN偺僥僉僗僩 (妛壢堦斒丄妛壢愱栧偺2嶜暘) 傪僲乕僩偵傑偲傔傑偟偨丅偦傟傑偱偼僥僉僗僩傪偨偩撉傓偩偗偱抦幆偑掕拝偟偨偮傕傝偵側偭偰偄偨偙偲偑攕場偲峫偊偨偨傔丄庤傪摦偐偡偙偲傪堄幆偟傑偟偨丅夁嫀栤偼11夞暘慡偰偺栤戣傪惓夝偡傞傑偱夝偒傑偟偨丅U-CAN偺夝愢晅偒偺夁嫀栤偼5夞暘偟偐側偐偭偨偨傔丄懠偺夞偺夝愢偵偮偄偰偼web忋偱専嶕偟偰偄傑偟偨丅傑偨丄夁嫀栤傪夝偄偰偄傞忋偱弶傔偰摼偨抦幆偼慡偰丄慜弎偺傑偲傔僲乕僩偵彂偒崬傫偱偄傑偟偨丅埲忋偺夁掱傪宱偰傛偆傗偔抦幆傪廫暘偵掕拝偝偣傞偙偲偑偱偒丄妛壢偵崌奿偱偒傑偟偨丅
4. 63夞
妛壢柶彍偺婜尷偼1擭偺偨傔丄崱夞傕偟棊偪偰偟傑偭偨傜師夞嫮偄惛恄揑側僾儗僢僔儍乕偑偐偐傞偲峫偊丄愨懳偵崌奿偟偨偄偲偄偆婥帩偪偱偟偨丅偟偐偟丄戝妛4擭師偺偨傔懖嬈尋媶傕峴傢側偗傟偽側傜偢丄枮懌偺偄偔曌嫮帪娫傪妋曐偱偒傑偣傫偱偟偨丅幚媄偺撪梕偼妛壢偵斾傋梱偐偵柺敀偐偭偨偨傔丄曌嫮傊偺儌僠儀乕僔儑儞偼崅偔丄偦偺暘曌嫮帪娫傪妋曐偱偒側偄偙偲偑傕偳偐偟偐偭偨偱偡丅曌嫮僗働僕儏乕儖偲偟偰偼丄9丒10寧偵U-CAN偺僥僉僗僩 (幚媄偵昁梫側抦幆傪傑偲傔偨1嶜暘) 傪僲乕僩偵傑偲傔丄11寧慜敿偵U-CAN偺僥僉僗僩 (幚媄偺楙廗栤戣傪傑偲傔偨1嶜暘) 傪夝偒丄11寧屻敿丒12寧偵夁嫀栤11夞暘傪1廃偟丄1寧偐傜夁嫀栤偺2廃栚偵擖傝傑偟偨丅夁嫀栤傪夝偄偰偄偨帪婜偼懖嬈尋媶偺捛偄崬傒帪婜偲廳側傝丄惛恄揑偵傕恎懱揑偵傕僴乕僪偱偟偨偑丄昁偢1擔侾偮偼夁嫀栤傪夝偔偲寛傔丄曌嫮偵椼傒傑偟偨丅杮斣偼丄愨懳偵庴偐傜側偗傟偽偲偄偆婥帩偪偑忋妸傝偟偰偟傑偭偰偁傑傝廤拞偱偒偢丄傑偨擄堈搙偑崅偐偭偨偙偲傕偁傝丄崌奿偱偒傑偣傫偱偟偨丅
5. 64夞
崱夞傕偟棊偪偨傜傑偨怳傝弌偟偵栠偭偰偟傑偆丄偲偄偆嫮偄僾儗僢僔儍乕偲愴偄側偑傜偺曌嫮偱偟偨丅僗働僕儏乕儖偲偟偰偼丄5寧偵U-CAN偺僥僉僗僩 (幚媄偵昁梫側抦幆傪傑偲傔偨1嶜暘)傪撉傒捈偟丄6寧偐傜帋尡傑偱U-CAN偺僥僉僗僩 (幚媄偺楙廗栤戣傪傑偲傔偨1嶜暘) 偲夁嫀栤20夞暘傪孞傝曉偟夝偒傑偟偨丅HP偵岞奐偝傟偰偄傞傕偺傛傝慜偺夁嫀栤偵偮偄偰偼丄榓揷偝傫偐傜捀偒傑偟偨丅63夞偺懳嶔偱婛偵埖偭偰偄偨嵟怴11夞暘偼1廃丄弶傔偰埖偆巆傝偺9夞暘偼2廃偟偨偺偪丄娫堘偊偨栤戣傪惓夝偡傞傑偱孞傝曉偟夝偒傑偟偨丅傑偨丄夁嫀栤偺墘廗傪恑傔傞拞偱働傾儗僗儈僗偑栚棫偪丄働傾儗僗儈僗偺桳柍偑崌斲傪暘偗傞偲姶偠偨偨傔丄杮斣慜擔偵偦傟傑偱偵偟偨働傾儗僗儈僗傪慡偰僲乕僩偵傑偲傔傑偟偨丅杮斣偼丄嬯庤側戜晽偑僥乕儅偵側偭偰偄偨傝丄尒偨偙偲偺側偄栤戣偑弌戣偝傟偨傝偟偰丄撪怱偐側傝徟傝傑偟偨偑丄63夞偺斀徣傪妶偐偟丄栚偺慜偺栤戣偵廤拞偡傞偙偲傪堄幆偟懕偗傑偟偨丅寢壥偵偮偄偰偼偁傑傝庤墳偊偑側偔丄晐偔偰帺屓嵦揰偱偒側偄傎偳偩偭偨偨傔丄崌奿傪抦偭偨帪偼偲偰傕嬃偒傑偟偨(徫)
傆傝偐偊偭偰
丂曌嫮偺夁掱偼偲偰傕戝曄偱偟偨偑丄摨帪偵妝偟偔傕偁傝傑偟偨丅摿偵懖嬈尋媶偲廳側偭
偰偄偨帪婜偼丄幚媄偺夁嫀栤傪夝偔偙偲偑椙偄婥暘揮姺偵側偭偰偄傑偟偨(徫)丂昁巰偱曌嫮偟偰崌奿傪彑偪庢偭偨偙偲偼帺怣偵宷偑偭偨偨傔丄偲偰傕椙偄恖惗宱尡偵側偭偨偲姶偠偰偄傑偡丅偙偙傪僑乕儖偲偡傞偺偱偼側偔丄偙傟偐傜傕擔忢揑偵揤婥恾摍偵怗傟丄梊曬媄弍傪杹偄偰偄偒偨偄偱偡丅嵟屻偵偼側傝傑偡偑丄偛巜摫偄偨偩偄偨榓揷偝傫丄墳墖偟偰偔偩偝偭偨尋媶幒偺奆偝傫偵丄怺偔姶幱怽偟忋偘傑偡丅
2025擭12寧UP
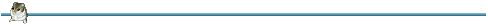
|
壨懞偝傫曇丂2022擭搤崌奿
|
偒偭偐偗
傕偲傕偲拞妛惗偺崰偐傜丄婥徾偺偙偲偵嫽枴偑偁傝丄條乆側寍擻恖偑婥徾梊曬巑偺帒奿傪帩偭偰TV偱妶桇偟偰偄傞偺傪尒偰丄奿岲椙偄側偁偲傏傫傗傝摬傟偰偄傑偟偨丅
戝妛1擭偺崰丄嫵堢妛晹偺慡堳偑庴島偡傞棟壢偺庼嬈偱丄昅曐愭惗偑乽婥徾梊曬巑偺帒奿偼帩偭偰偄偰偡偛偔椙偄傛乿偲嬄偭偰偄偨偙偲偑嫮偔報徾偵巆偭偰偄傑偟偨丅
偦偆偟偰丄妛晹2擭偵側傞僞僀儈儞僌偱昅曐愭惗偵儊乕儖傪偟丄婥徾梊曬巑帋尡懳嶔島嵗丄捠徧乬儅僢僗儖摴応乭偵擖傟偰偄偨偩偒傑偟偨丅
摴偺傝
2020 擭係寧 杮奿揑側帋尡曌嫮奐巒
2021 擭俈寧 幚媄偺僥僉僗僩傪攦偆
2021 擭俉寧 庴尡乮妛壢堦斒崌奿乯
2022 擭侾寧 庴尡乮妛壢愱栧丒幚媄崌奿乯
2022 擭俁寧 婥徾梊曬巑 帒奿庢摼
侾丏帋尡曌嫮奐巒乮妛晹俀擭 弔乯
儅僢僗儖摴応偑僆儞儔僀儞壔偟偨帪婜偱丄Zoom偱嶲壛偟傑偟偨丅
嶲峫彂偼丄巹偑拞妛惗偺崰偵曣偑攦偭偰偔傟偨妛壢堦斒偺僥僉僗僩偵丄摨偠僔儕乕僘偺妛壢愱栧傪攦偄懌偟丄弴斣偵彮偟偢偮撉傒恑傔傞偙偲偵偟傑偟偨丅
俀丏帋尡1儢寧慜偵幚媄偺僥僉僗僩傪攦偆乮妛晹俁擭 壞乯
偦傠偦傠妛壢偺曌嫮傕堦捠傝廔傢傞偩傠偆偲偄偆偙偲偱丄帋尡傪怽偟崬傒傑偟偨丅偟偐偟丄幚媄偺曌嫮偼偁傑傝偟偰偍傜偢丄儅僢僗儖摴応偺拞偱壗夞偐夝偄偨掱搙偱偡丅壗廫暥帤傕彂偔婰弎栤戣偱偼丄堦偐傜帺暘偺尵梩偱婥徾偵偮偄偰愢柧偡傞偙偲偑傎偲傫偳偱偒傑偣傫偱偟偨丅偲傝偁偊偢夁嫀栤傪夝偒丄幚媄偺僥僉僗僩傪夝偒丄側傫偲偐夝摎梡巻傪杽傔傜傟傞偔傜偄偺晅偗從偒恘傪実偊傑偟偨丅
俁丏偼偠傔偰偺庴尡乮妛晹俁擭 壞乣廐乯
幚媄偼傕偪傠傫丄妛壢愱栧偺撪梕偱偡傜媫偄偱媗傔崬傫偩偺偱丄偲傝偁偊偢妛壢堦斒偩偗偱傕崌奿偱偒偨傜側偁偲偄偆婥帩偪偱偟偨丅帋尡慜擔偱偡傜崌奿儔僀儞偵払偟偨偙偲偑側偐偭偨偺偵丄摉擔丄峴偒妡偗偺揹幵偱媗傔崬傫偩偺偑岟傪憈偟偨偺偐丄妛壢堦斒偩偗崌奿偱偒傑偟偨丅
係丏曌嫮曽朄傪曄偊傞乮妛晹俁擭 廐乯
崱傑偱偼丄帺暘偱僲乕僩傪嶌偭偰暘偐傝傗偡偔傑偲傔傞曽朄偱曌嫮偟偰偄傑偟偨偑丄崱傑偱嶌偭偨僲乕僩傪曗彆嫵嵽偲偟偰丄嶲峫彂傪堦尵堦嬪挌擩偵撉傒崬傓曽朄傪儊僀儞偵曄偊傑偟偨丅擺摼偡傞傑偱暥復傪撉傒丄楙廗栤戣傪夝偒丄夝愢傪撉傫偱暘偐傜側偐偭偨傜傑偨嶲峫彂偺條乆側儁乕僕傪奐偔丄偲偄偆棳傟傪嶌傝傑偟偨丅偦傟偑偩偄傇帺暘偵崌偄丄傛偔棟夝偱偒傞傛偆偵側傝傑偟偨丅
俆丏2夞栚偺帋尡乮妛晹俁擭 搤乯
妛晹偺妛婜枛帋尡婜娫恀偭扅拞偱偺婥徾梊曬巑帋尡偱偟偨丅偦傟偱傕寗娫帪娫傪忋庤偔尒偮偗偰嶲峫彂傪撉傒崬傫偩偲巚偄傑偡丅幚媄偵娭偟偰偼丄傕偪傠傫慜夞傛傝傕傗傝崬傫偱偒傑偟偨偑丄柾媅帋尡偱崌奿儔僀儞偵忔偭偨偙偲偼堦搙傕偁傝傑偣傫偱偟偨丅帪娫撪偵側傫偲偐廔傢傜偣偨幚媄偼丄帺暘偺夝摎傪傎偲傫偳儊儌偟偰偍傜偢丄帺屓嵦揰偑擄偟偐偭偨偺偱偡偑丄夝偄偨姶妎偲偟偰偼丄崌奿偼屲暘屲暘偔傜偄偩傠偆偲巚偭偰偄傑偟偨丅偟偐偟丄傑偨傕傗峴偒妡偗偺揹幵偱媗傔崬傫偩偺偑岟傪憈偟偨偺偐丄崌奿偱偒傑偟偨丅
傆傝偐偊偭偰
巚偊偽丄棟壢愱峌偺妛晹3擭惗埲忋偺妛惗偑傎偲傫偳偱偁傞儅僢僗儖摴応偵丄壒妝愱峌偺2擭惗偲偟偰嶲壛偟丄偦偺屻挿偔懕偗傜傟偨偺偼婱廳側宱尡偱偡丅庼嬈偵傕傛偔弌惾偟偰偄偰丄榓揷愭惗偵乽壒妝愱峌側偑傜傛偔怘傜偄偮偄偰偒偰偄傑偡偹乿偲偄偆傛偆側偙偲傪尵傢傟偨偲偒偼丄側傫偩偐帺暘偑偍偐偟偔偰徫偭偰偟傑偄傑偟偨丅
1擭栚偼僆儞儔僀儞偲偄偆偙偲傕偁傝丄堦恖偱曌嫮偟偰偄傞姶妎偑嫮偐偭偨偺偱偡偑丄2擭栚偵懳柺偵側傝丄桭払偲堦弿偵儅僢僗儖摴応偵捠偊偨偙偲偼丄杮摉偵怱嫮偐偭偨偱偡丅
埫婰偵嬯庤堄幆偑偁傝丄戝曄側偙偲傕偁傝傑偟偨偑丄幚惗妶偲徠傜偟崌傢偣側偑傜傛偔棟夝偡傞偙偲偱丄婥徾偭偰柺敀偄側偁偲偄偆弮悎側嫽枴傪帩偭偰妝偟偔曌嫮偱偒傑偟偨丅
崱夞崌奿偟丄怽惪偟偨偙偲偱乽婥徾梊曬巑乿偲偄偆尐彂偒傪帩偮偙偲偵偼側傝傑偡偑丄帺暘偵偼傑偩抦傜側偄偙偲偑偨偔偝傫偁傝傑偡丅偙偺尐彂偒偵抪偠偸傛偆丄偙傟偐傜傕偭偲傕偭偲丄妝偟傫偱妛傫偱偄偒偨偄偱偡丅
|
2022擭3寧UP
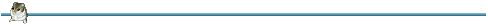
|
戝媣曐偝傫曇丂2021擭壞崌奿
|
偒偭偐偗
戝妛1擭偵昅曐愭惗偺乽婥徾妛擖栧乿偲偄偆庼嬈傪庴偗偰丄乽婥徾妛乿偲偄偆妛栤傪抦傝傑偟偨丅婥徾偵娭楢偡傞僄僺僜乕僪傗帺恎偺宱尡側偳傕岎偊偨嫽枴怺偄庼嬈偱丄婥徾偺偙偲傪慡慠抦傜側偐偭偨巹偼堷偒崬傑傟偰偄偒傑偟偨丅偁傞夞偱愭惗偼婥徾梊曬巑帋尡傪庴偗傞偙偲偺儊儕僢僩傪榖偟偰偔偩偝傝丄巹偼嫽枴傪帩偪傑偟偨丅惃偄偺傑傑僥僉僗僩傪攦偭偨傕偺偺丄妛壢偺愝寁壽戣偑朲偟偔側傝彮偟恑傔偨偲偙傠偱僥僉僗僩偼杮扞偵曻抲偝傟傑偟偨丅偟偐偟2擭屻丄僐儘僫壭偱戝妛偺庼嬈偑側偔側傝晹妶偑嬛巭偝傟撍擛壣偵側偭偨偙偺帪娫傪柍懯偵偟偨偔側偄偲巚偄丄壗偐偟傛偆偲峫偊偰偄偨偲偙傠丄杮扞偵曻抲偝傟偰偄傞梊曬巑帋尡偺僥僉僗僩傪尒偮偗傑偟偨丅偦偆偟偰嵞傃堦偐傜曌嫮偟巒傔傑偟偨丅
摴偺傝
2020擭4寧丂帋尡曌嫮奐巒
2020擭8寧丂54夞庴尡(堦斒乑丄愱栧亊丄幚媄庴偗偢)
2021擭1寧丂55夞庴尡(堦斒柶彍丄愱栧乑丄幚媄亊)
2021擭8寧丂56夞庴尡(堦斒柶彍丄愱栧柶彍丄幚媄乑)
2021擭10寧丂婥徾梊曬巑丂帒奿庢摼
侾丏54夞帋尡傑偱
僥僉僗僩偼亀傜偔傜偔撍攋丂婥徾梊曬巑偐傫偨傫崌奿僥僉僗僩亁傪巊梡偟傑偟偨丅曌嫮偺棳傟偲偟偰偼丄傜偔傜偔偺僥僉僗僩傪撉傓仺1偮偺復偑廔傢偭偨傜丄傜偔傜偔偺楙廗栤戣傪夝偔仺惛慖栤戣廤偺奩摉偡傞晹暘傪夝偔仺娫堘偊偨栤戣偺夝偒捈偟偲偄偭偨姶偠偱偟偨丅嵟屻偺2廡娫偼偙偺夝偒捈偟傪孞傝曉偟偮偮丄婥徾嬈柋巟墖僙儞僞乕偵偁傞嵟嬤偺夁嫀栤傪夝偒傑偟偨丅
丂側偍丄摉弶偼54夞偱妛壢2壢栚撍攋傪栚昗偲偟偰偄傑偟偨偑愱栧偺僥僉僗僩偑慡慠恑傑偢丄堦斒愱栧慡棊偪傪旔偗傞偨傔偵傕帋尡1偐寧傎偳慜偐傜堦斒偺傒偵峣傞偙偲偵偟傑偟偨丅
俀丏54夞帋尡
丂54夞帋尡偱偼妛壢堦斒偲丄儅乕僋幃偺壜擻惈傪怣偠偰妛壢愱栧傪庴偗傑偟偨丅幚媄偼曌嫮偟偰偄側偐偭偨偨傔庴偗偢偵婣偭偨偺偱偡偑丄屻偐傜宱尡偲偟偰庴偗偨曽偑椙偄偲偄偆偙偲傪抦傝傑偟偨(徫)丅寢壥偼堦斒偑11/15(11)丄愱栧偑9/15(11)偱丄僊儕僊儕偱偟偨偑堦斒偺崌奿傪柍帠僎僢僩偱偒傑偟偨(仸僇僢僐撪偼崌奿婎弨)丅
俁丏54夞帋尡屻乣55夞帋尡傑偱
丂壞乣搤偼5偐寧偟偐側偄偺偱丄54夞偺帋尡屻偡偖偵愱栧偺巆傝偺晹暘偵庢傝妡偐傝傑偟偨丅偲摨帪偵幚媄偺僥僉僗僩(妛壢偲摨偠僔儕乕僘)傕峸擖偟丄曌嫮傪巒傔傑偟偨丅
幚媄偺棳傟偼丄僥僉僗僩慜敿傪撉傒恑傔傞(乣11寧拞弡)仺僥僉僗僩屻敿偺帠椺墘廗傪2廃傎偳(乣12寧拞弡)仺夁嫀栤墘廗偲偄偭偨姶偠偱偟偨丅側偍丄婥徾嬈柋巟墖僙儞僞乕偵偼悢擭暘偺夁嫀栤偟偐嵹偭偰偄側偄&摎偊偺傒偱夝愢偑側偄偲偄偆偙偲偱丄栤戣偲夝愢偼庡偵乽傔偞偰傫僒僀僩乿傪妶梡偟傑偟偨丅傔偞偰傫僒僀僩偼20夞暘偺夁嫀栤偲夝愢傪尒傞偙偲偑偱偒丄撈妛偺嫮偄枴曽偱偟偨丅
係丏55夞帋尡
丂55夞偼堦斒偑柶彍偺偨傔丄愱栧偲幚媄傪庴尡偟傑偟偨丅幚媄偼夁嫀栤偱尒偨偙偲偺側偄栤戣偵偆傠偨偊懪偪偺傔偝傟傑偟偨丅寢壥偼丄愱栧偑10/15(9)丄幚媄侾偑45揰丄幚媄俀偑55揰仺摼揰棪50%(60%)偱丄愱栧偼側傫偲偐崌奿丄幚媄偼10%(20揰)傎偳懌傝偢晄崌奿偱偟偨(仸僇僢僐撪偼崌奿婎弨)丅
俆丏55夞帋尡屻乣55夞崌奿敪昞傑偱
丂55夞帋尡懳嶔偱幚媄偺夁嫀栤偺懡偔偼夝偄偰偄偨偺偱丄師偺帋尡傑偱7偐寧偁傞偙偲傕峫椂偟丄偡偖偵偼曌嫮傪嵞奐偟傑偣傫偱偟偨丅偦偺戙傢傝丄偙傟傑偱傎偲傫偳偟偰偙側偐偭偨撉彂傪偟巒傔傑偟偨丅巹偼婥徾尰徾偵偮偄偰偺抦幆偑朢偟偐偭偨偺偱丄婥徾偵娭偡傞杮傪撉傓偙偲偱曌嫮偟偨撪梕偺偍偝傜偄偑偱偒偨傝丄壗傛傝婥徾偭偰柺敀偄側偲偄偆婥帩偪傪嵞妋擣偱偒傑偟偨丅
丂傑偨偙偺帪婜偵昅曐愭惗偺尋媶幒朘栤傪偟偨偙偲偱丄尋媶幒偺儊儞僶乕偲抦傝崌偊偨傝丄儅僢僗儖摴応偵嶲壛偝偣偰傕傜偊傞偙偲偵側傝傑偟偨丅偙傟傑偱婥徾偵嫽枴偺偁傞恖偨偪偲幚嵺偵夛偭偰偍榖偟偡傞婡夛偼側偐偭偨偺偱丄怴慛偱偲偰傕妝偟偄帪娫偱偟偨丅
俇丏55夞崌奿敪昞乣56夞帋尡傑偱
丂巆傝偑幚媄偩偗偵側偭偨偺偱3寧拞偼撉彂偵傆偗傝丄4寧偐傜嵞傃幚媄偺夁嫀栤傪夝偒巒傔傑偟偨丅偟偐偟55夞偺帋尡懳嶔偲摨條偵丄弶尒偺栤戣偼壗傪暦偐傟偰偄傞偺偐棟夝偡傞偺偵帪娫偑偐偐傝帋尡帪娫撪偵廔傢傜側偄丄惓摎棪偑儃乕僟乕偵撏偐側偄偲偄偭偨姶偠偱偟偨丅偙偺傑傑夁嫀栤墘廗傪懕偗偰偄偰傕55夞偲摨偠傛偆側寢壥偵側傞偲嶡偟丄曌嫮朄傪曄偊傑偟偨丅怴偟偄曌嫮朄偲偟偰偼乽忥棎儊儌乿偲乽嬯庤儊儌乿傪嶌傝傑偟偨丅乽忥棎儊儌乿偼幚媄偱弌偰偔傞婥徾尰徾傪帺暘偱傑偲傔捈偟丄夁嫀栤偱弌偰偒偨怴偨側婥偯偒傪搒搙彂偒壛偊偰偄偒傑偟偨丅乽嬯庤儊儌乿偼働乕僞僀偺儊儌傾僾儕偵夁嫀栤偱嬯庤偩偭偨揰傗柾斖夝摎偱巊傢傟傞尵梩偺僯儏傾儞僗側偳傪彂偒傑偟偨丅偙傟傜擇偮傪夁嫀栤墘廗偺崌娫偵尒捈偡偲偄偆曌嫮朄偵曄偊偨偲偙傠丄彮偟偢偮栤戣偺堄恾傪棟夝偱偒傞傛偆偵側傝傑偟偨丅帋尡夛応偱偺嵟屻偺妋擣偵傕巊偊傞偺偱僆僗僗儊偱偡丅
俈丏56夞帋尡
丂晛抜杮斣偵庛偄僞僀僾側偺偱偡偑丄偙偺擔偼嬃偔傎偳椻惷偵帋尡偵椪傔傑偟偨丅崌奿敪昞傑偱偺40擔娫偼偲偰傕挿偔姶偠傑偟偨偑丄帺暘偺庴尡斣崋傪尒偮偗偨偁偺擔偺岾偣側弖娫偼偙偺愭傕朰傟側偄偲巚偄傑偡丅
丂帋尡屻偡偖偵嶌惉偟偨嵞尰摎埬傪嶲峫偵嵦揰偟偨偲偙傠丄幚媄1偑69揰丄幚媄2偑75揰仺摼揰棪72亾(65%)偱偟偨(仸僇僢僐撪偼崌奿婎弨)丅
傆傝偐偊偭偰
崌奿偡傞偨傔偵傕偪傠傫検偼昁梫偱偡偑丄偄偐偵忣曬嫮幰偱偄傞偐偑崌斲偺1揰傪嵍塃偡傞偲巹偼庴尡偟偰傒偰姶偠傑偟偨丅椺偊偽愱栧帋尡偼擔乆峏怴偝傟偰偄傞撪梕側偺偱丄僥僉僗僩偲撪梕偑曄傢偭偰偄傞揰偑懡偔偁傝傑偡丅幚嵺巹偼梊曬巑帋尡庴尡惗偲忣曬傪嫟桳偟偰偄偨偙偲偱媬傢傟偨1揰偑偁傝傑偟偨丅
丂愭惗偑庼嬈偱嬄偭偰偄偨傛偆偵丄婥徾梊曬巑帋尡偵挧愴偟偨偍偐偘偱偨偔偝傫偺儊儕僢僩偑偁傝傑偟偨丅傑偨嬻傪挱傔傞偺偑崱偼堦憌妝偟偄偱偡丅婥徾梊曬巑帋尡偼壗嵨偱傕扤偱傕挧愴偱偒傞慺揋側帒奿側偺偱丄崱屻傕婥徾偵嫽枴傪帩偮恖偑憹偊偰偄偭偨傜椙偄側偲巚偄傑偡丅
|
2022擭3寧UP
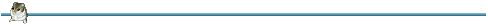
|
垻晹偝傫曇丂2021擭壞崌奿
|
偒偭偐偗
崅峑惗偺帪偐傜側傫偲側偔婥徾偵嫽枴偑偁傝丄枅擔偺揤婥梊曬僠僃僢僋偟偨傝丄柺敀偄塤偺幨恀偼僗儅儂偱嶣塭偟偨傝偟偰偄傑偟偨丅彨棃偼杊嵭偵実傢傞巇帠偵廇偒偨偄側偲戝妛偱偼暿暘栰(朄棩宯)傪愱峌偟傑偟偨丅戝妛偱婥徾妛偺島媊傪偲偭偨嵺丄愭惗偵婥徾偵嫽枴偑偁傞偲榖偟偨偲偙傠丄暥宯偱偁偭偰傕婥徾梊曬巑偺帒奿偼庢傟傞偐傜僠儍儗儞僕偟偰傒偰偼丠偲採埬偟偰偄偨偨偩偄偨偺偑曌嫮傪巒傔偨偒偭偐偗偱偡丅庯枴偲偟偰婥徾偵偮偄偰曌嫮偟丄榬帋偟偱婥徾梊曬巑帋尡傕庴偗偰傒傛偆丄戝妛懖嬈傑偱偵崌奿偡傞偙偲傪栚昗偵僗僞乕僩偟傑偟偨丅
摴偺傝
? 堦斒抦幆
乽堦斒婥徾妛 戞2斉曗掶斉乿(彫憅媊岝, 2016)傪峸擖偡傞傕奀柺峏惓婥埑偲崀悈夁掱偺偲偙傠偱偮傑偢偄偨偨傔丄嶲峫彂丗乽婥徾梊曬巑偐傫偨傫崌奿僥僉僗僩乹妛壢丒堦斒抦幆曇乺乿(婥徾梊曬巑帋尡庴尡巟墖夛, 2008)傪峸擖偟偰曌嫮傪奐巒偟傑偟偨丅
曌嫮弶擔偵丄嵟怴偺夁嫀栤傪夝偄偰傒傞傕慡偔帟偑棫偨偢丄夁嫀栤傪偲偵偐偔孞傝曉偟夝偔偲偄偆偺偼掹傔丄乽婥徾梊曬巑娙扨崌奿僥僉僗僩乹妛壢丒堦斒抦幆曇乺乿傪傑偢堦廃偡傞偙偲偵寛傔傑偟偨丅堦廃撉傫偩屻偵偼夁嫀栤偺朄椷偺栤戣埲奜偱傢偐傜側偄傕偺偼丄2,3栤偵傑偱尭偭偰崌奿儔僀儞偵傕忔傞傛偆偵側傝傑偟偨丅
朄椷偼4栤傎偳弌偰旕忢偵摼揰尮偵側傞偺偱愨懳棊偲偣側偄側偲巚偄丄乽婥徾嬈柋娭楢朄椷廤 2020擭搙斉乿乮婥徾嬈柋巟墖僙儞僞乕, 2020乯傪峸擖偟丄昿弌偺忦暥傪僠僃僢僋偟傑偟偨丅
夁嫀栤偼10擭暘夝偄偰偐傜岦偐偄傑偟偨丅
? 愱栧抦幆
屄恖揑偵丄愱栧偑嵟傕嬯愴偟傑偟偨丅2夞栚偺帋尡偱愱栧傪崌奿偡傞偙偲傪栚昗偵偟偰偄傑偟偨偑丄婥徾塹惎夋憸偺撉傒庢傝傗丄僂僀儞僪僾儘僼傽僀儔丄ENSO傗丄娤應婡婍偺栤戣側偳偱幐揰偟偰偟傑偄傑偟偨丅2夞栚偺帋尡偼幚媄偺曌嫮偵偼庤傪弌偟偰偄側偐偭偨偺偱偡偑偦傟偑攕場偺傛偆偵巚偄傑偡丅
夁嫀栤傪10夞暘傗偭偰偄偨偙偲偱枮懌偟偰偄偨偺偱偡偑丄夁嫀栤傪埫婰偟偰偄偨偩偗偱棟夝偑怺傑偭偰偍傜偢杮斣懳墳偱偒傑偣傫偱偟偨丅婥徾挕偺儂乕儉儁乕僕偺乽抦幆丒夝愢乿(https://www.jma.go.jp/jma/menu/menuknowledge.html)傪傂偨偡傜撉傫偱偐傜庴偗偨傜撍攋偡傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅
? 幚媄
嵟屻偺帋尡偼丄幚媄偺傒偺庴尡偩偭偨偨傔丄側傫偲偐崌奿偡傋偔儅僢僗儖摴応偵嶲壛偝偣偰偄偨偩偒傑偟偨丅偦傟傑偱丄扤偐偵幙栤偱偒傞婡夛偑側偐偭偨偨傔丄婰弎栤戣傗恾傪揧嶍偟偰偄偨偩偗偨偙偲偼旕忢偵戝偒側僾儔僗偵側傝傑偟偨丅
300hPa柺偺僕僃僢僩傗500hPa柺偺僩儔僼丄850hPa傗増娸慜慄偺嶌恾傗丄僩儔僼偺捛愓偺巇曽乮怺傑傞丒愺偔側傞丒偦傟偵傛偭偰掅婥埑偑敪払偡傞偐乯摍偺億僀儞僩傪捦傓偙偲偑偱偒偨偺偱丄帪娫傪偐偗偢偵攝揰偺崅偄栤戣偺惓摎棪傪忋偘傞偙偲偑偱偒傞傛偆偵側傝傑偟偨丅
偦傟傑偱偼夁嫀栤傪夝偄偰偄偰傕60揰慜屻乮帪偵偼50揰偔傜偄偺帪傕乯偽偐傝偩偭偨偺偱偡偑丄偦偺屻偼戝懱70揰埲忋丄2廃栚偵偼偍傛偦90揰埲忋傪庢傟傞傛偆偵側偭偰偄傑偟偨丅
夁嫀栤偼嵟廔揑偵丄7擭暘傪2廃乮2廃栚偵85揰傪峴偐側偐偭偨傕偺偵偮偄偰偼3廃偟傑偟偨乯偟偰杮斣偵椪傒傑偟偨丅
夁嫀栤傪夝偄偰偄偰婥傪偮偗偨偙偲偼丄
嘆幚媄偼夝摎梡巻偑4儁乕僕偁傞偺偱1儁乕僕偁偨傝15暘偱夝偒恑傔傞乮巆傝15暘尒捈偟乯傛偆堄幆偟偨偙偲偱偡丅婰弎側偳僷僢偲摎偊偺傢偐傜側偄傕偺偼丄屻偺栤戣傪尒偨屻偺傎偆偑傢偐傝傗偡偄傕偺傕偁傞偺偱堦搙旘偽偟偰丄巆傝15暘偺娫偵傕偆堦搙婣偭偰偒偰峫偊捈偡傛偆偵偟傑偟偨丅屻敿偺寠杽傔栤戣偼偲偰傕娙扨偱摼揰尮偩偭偨傝偡傞偺偱嬻敀偺傑傑弌偡偙偲偼愨懳側偄曽偑偄偄偲巚偄傑偡両
嘇掅婥埑拞怱傪捛愓偡傞栤戣偼丄戝懱偺埵抲傪姶妎偱僾儘僢僩偡傞偲幐攕偡傞偙偲偑懡偄偺偱丄僐儞僷僗傪巊偭偰僾儘僢僩偟偰偄傑偟偨丅
嘊愒偲惵偲墿怓偺僼儕僋僔儑儞偺寀岝儁儞傪巊偭偰恾傪怓暘偗偟偰偄傑偟偨丅乮掅婥埑丒僩儔僼丒壏抔慜慄偼愒丄崅婥埑丒姦椻慜慄偼惵丄300hPa嫮晽幉夝愅丒幖悢丒崀悈堟側偳偼墿怓偲偄偆嬶崌偵丄偍偍傛偦偺怓傪寛傔偰偄傑偟偨丅乯
幚媄帋尡偼丄婰弎偺栤戣傪堦岅堦嬪摨偠傛偆偵彂偗傞傛偆偵埮塤偵婰弎偺僷僞乕儞傪妎偊傞偲偄偆傛傝傕丄嶌恾偺億僀儞僩傗恾偺尒曽傪尋媶偡傞曽偑桳塿偩側偲姶偠傑偟偨丅
傆傝偐偊偭偰
弶傔偼丄1夞栚偱堦斒崌奿丄2夞栚偱愱栧崌奿丄3夞栚偱幚媄崌奿偺僔僫儕僆傪側傫偲側偔昤偄偰偄偨偺偱偡偑丄嵟廔揑偵6夞傕庴偗偰偟傑偄傑偟偨乧両
僗僞乕僩摉帪偼丄抧忋揤婥恾偟偐尒偨偙偲偑側偔丄崅婥埑丒掅婥埑丒慜慄4偮丒曃惣晽偔傜偄偟偐傢偐傜偢丄夁嫀栤傪尒偰傕傎傏壗傕傢偐傝傑偣傫偱偟偨両徫
儅僢僗儖摴応偵嶲壛偡傞傑偱丄廃傝偵婥徾梊曬巑帋尡偺曌嫮傪偟偰偄傞恖偑傎偲傫偳偍傜偢丄幙栤偱偒傞恖傕偄側偄忬懺偩偭偨偺偱丄旕忢偵旕岠棪揑側曌嫮傪懕偗偰偄偨側両偲崱峫偊傟偽巚偄傑偡丅徫
儅僢僗儖摴応偵嶲壛偡傞傑偱偼丄夁嫀栤傪夝偄偰娫堘偊偨栤戣偺棟桼傪挷傋傞偺偵朿戝側帪娫傪巊偭偰偄傑偟偨丅摿偵幚媄偺嶌恾栤戣偼丄旝柇偵僩儔僼傗慜慄偺挿偝偑堘偭偨傝丄堒搙宱搙偺撉傒庢傝偑1搙堘偄偩偭偨傝偱丄晄惓夝側偙偲偑懡偔丄側偤娫堘偭偨偺偐丄夝摎偑側偤偦偆側傞偺偐旝柇偵棟夝偱偒側偄偱傕傗傕傗偟偰偄傞偙偲偑懡偐偭偨偱偡丅幚媄偺曌嫮傪偟偰栺敿擭宱偭偰傕夁嫀栤偑60揰慜屻偟偐庢傟偢偳偆偟偨傜椙偄偐懅媗傑偭偰偄偨僞僀儈儞僌偱儅僢僗儖摴応偵嶲壛偟偰丄榓揷偝傫偵幙栤偟偰媈栤傪夝徚偟偨偙偲偱丄帺暘偱傕嬃偔偔傜偄揰悢偑怢傃傑偟偨丅榓揷偝傫杮摉偵偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅廃傝偵幙栤偑偱偒傞恖偑偄側偄曽偼丄娫堘偄側偔丄幙栤偱偒傞恖傪尒偮偗偨曽偑偄偄偱偡両
梋択偱偡偑丄戝妛惗偵偲偭偰丄1寧枛偺帋尡偼丄婜枛帋尡偺擔掱偲娵偐傇傝偟偨傝8寧偺帋尡偐傜栺5儢寧偟偐曌嫮帪娫偑庢傟側偄偺偱寢峔偟傫偳偐偭偨偱偡乧両妛惗偺曽偼寁夋揑偵丄偦偟偰8寧偺帋尡偵偼慡椡偱彑晧偐偗偵峴偭偨曽偑偄偄偲巚偄傑偡両
側偐側偐崌奿傑偱帪娫偼偐偐偭偰偟傑偄傑偟偨偑丄曌嫮偟偰偄偰忢偵偲偰傕妝偟偐偭偨偱偡両偳暥宯偱傕傎偲傫偳僛儘抦幆偱傕懕偗偰偄傟偽愨懳崌奿偱偒傑偡両偲曌嫮偟傛偆偲偟偰偄傞丒偟偰偄傞傒側偝傫偵揱偊偨偄偱偡両
|
2022擭3寧UP
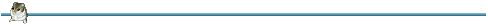
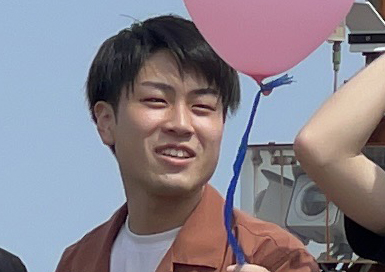 偍偙傔曇丂2020擭壞偄偭傁偮崌奿 偍偙傔曇丂2020擭壞偄偭傁偮崌奿
|
偒偭偐偗
崅峑偺帪偐傜抧妛偑岲偒偩偭偨偺偱偡偑丄偦偺拞偱傕婥徾妛偼嬯庤偱崕暈偟偨偄偲巚偄丄戝妛俁擭惗偺尋媶幒攝懏偱昅曐愭惗偺尋媶幒偵擖傜偣偰偄偨偩偒傑偟偨丅偲偼偄偊丄偨偩枱慠偲婥徾妛傪曌嫮偡傞偺偱偼儌僠儀乕僔儑儞偑曐偰側偄偲峫偊丄堦偮偺栚昗偲偟偰婥徾梊曬巑帋尡崌奿傪栚巜偡偙偲偵偟傑偟偨丅
摴偺傝
俀侽俀侽擭係寧丂帋尡曌嫮奐巒
俀侽俀侽擭俉寧丂庴尡乮崌奿乯仌 婥徾梊曬巑丂帒奿庢摼
侾丏婥徾偺擖栧彂傪撉傓乮俀侽俀侽擭俁寧乣乯
丂傑偩昅曐尋媶幒偵攝懏偝傟傞偐偳偆偐枹妋掕側帪婜偩偭偨偺偱丄杮奿揑側帋尡曌嫮偼偟偰偄傑偣傫偱偟偨丅偨偩丄攝懏偝傟偨帪偵婥徾偵娭偡傞抦幆偑侽偩偲崲傞偲峫偊丄偲傝偁偊偢娙扨側婥徾偺擖栧彂傪撉傒傑偟偨丅婥徾梊曬巑帋尡偵崌奿偟偨偄偩偗偱偁傟偽丄弶傔偐傜帋尡懳嶔偺嶲峫彂傪撉傫偩傎偆偑岠棪揑偩偲巚偄傑偡丅
嶲峫恾彂丗僩僐僩儞恾夝婥徾妛擖栧
俀丏妛壢堦斒偺帋尡懳嶔傪峴偆乮係寧乣俆寧拞弡乯
丂惏傟偰昅曐尋媶幒偵攝懏偝傟偨偨傔丄婥徾梊曬巑帋尡偺曌嫮傪巒傔傑偟偨丅壞偺帋尡偱妛壢俀庬椶崌奿傪戞堦栚昗偵掕傔丄妛壢堦斒偺嶲峫彂傪峸擖偟傑偟偨丅妛壢堦斒偼丄婥徾偵偍偗傞婎慴揑側暔棟妛偺撪梕偑懡偄偺偱丄崅峑偱暔棟傪棜廋偟偰偄偨巹偼彮偟傾僪僶儞僥乕僕偑偁傝傑偟偨丅慖傫偩嶲峫彂偼恾傗怓偑懡偔丄婥徾弶怱幰偵偼偲偭偮偒傗偡偄嶌傝偱偟偨丅乽堦斒婥徾妛乿偑擄偟偔姶偠傞恖偼丄偙偪傜傪僆僗僗儊偟傑偡丅怮傞慜偵彮偟偢偮撉傒恑傔丄堦偐寧敿偐偗偰撉傒愗傝傑偟偨丅搑拞偵宖嵹偝傟偨椺戣傕夝偒傑偟偨丅
嶲峫恾彂丗婥徾梊曬巑娙扨崌奿僥僉僗僩亙妛壢丒堦斒抦幆曇亜
俁丏妛壢愱栧偺帋尡懳嶔傪峴偆乮乣俇寧乯
丂師偵丄妛壢愱栧偺嶲峫彂傪峸擖偟丄曌嫮偟傑偟偨丅屄恖揑偵偼丄妛壢愱栧偺曌嫮偑堦斣恏偐偭偨偱偡丅撪梕偑弮悎側埫婰偽偐傝偱丄偐偮検傕懡偔丄妛壢堦斒偲斾妑偟偰撉傓偺偵帪娫偑偐偐傝傑偟偨丅慡晹傪姰帏偵偡傞偺偼戝曄側偺偱丄抁帪娫梊曬側偳偺廳梫崁栚偵廳揰傪抲偄偰撉傒傑偟偨丅嬻偒帪娫側偳傪巊偭偰丄側傫偲偐俇寧拞偵撉傒愗傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅搑拞偵宖嵹偝傟偨椺戣傕夝偒傑偟偨丅
嶲峫恾彂丗婥徾梊曬巑娙扨崌奿僥僉僗僩亙妛壢愱栧抦幆曇亜
係丏妛壢堦斒丒愱栧偺帋尡栤戣傪夝偔乮乣俈寧壓弡乯
丂偙偙傑偱偱丄妛壢堦斒丒愱栧偺僀儞僾僢僩偑廔傢偭偨偺偱丄崱搙偼巗斕偺栤戣廤傪梡偄偰丄傾僂僩僾僢僩傪峴偄傑偟偨丅娫堘偊偨栤戣偼嶲峫彂偱挷傋偰妛廗偟側偍偟丄栤戣廤偺妛壢斖埻偺傒傪1廃偟傑偟偨丅杮奿揑側抦幆偺掕拝傪峴偆偲偲傕偵丄帋尡栤戣姷傟偑偱偒傑偟偨丅
嶲峫恾彂丗婥徾梊曬巑帋尡惛慖栤戣廤俀侽俀侽擭斉
俆.幚媄偺帋尡懳嶔傪峴偆乮俈寧壓弡乣俉寧乯
丂摉弶偺梊掕偱偼丄妛壢偺傒偺崌奿傪栚昗偵偟偰偄傑偟偨偑丄偙偙偵偒偰妛壢偺曌嫮偵朞偒偰偟傑偄丄柍懯偵偼側傜側偄偩傠偆偲巚偄丄婥暘揮姺偵幚媄帋尡懳嶔傪巒傔傑偟偨丅幚媄帋尡偺嶲峫彂傪峸擖偟偨偺偱偡偑丄抦幆偼夝偒側偑傜恎偵晅偗偨傎偆偑岠棪偑傛偄偲峫偊丄慜敿晹暘偺抦幆儁乕僕偼撉傑偢丄屻敿晹暘偵婰嵹偝傟偨椺戣傪偄偒側傝夝偒傑偟偨丅幚嵺偺婥徾梊曬巑帋尡偲偼栤戣宍幃偑堎側偭偰偄傑偟偨偑丄幚媄帋尡偺婎慴揑側抦幆傪恎偵晅偗傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅摿偵丄夝愢偑偲偰傕挌擩偱偁偭偨揰偑丄幚媄偺擖栧彂偲偟偰揔偟偰偄傑偟偨丅
丂師偵丄婥徾梊曬巑帋尡偺夁嫀栤傪婥徾嬈柋巟墖僙儞僞乕偐傜僟僂儞儘乕僪偟丄侾侽擭暘夝偒傑偟偨丅嵟弶偼係侽乣俆侽揰戙偱偟偨偑丄侾俆帠椺夝偄偨偁偨傝偱儃乕僟乕儔僀儞偺俈侽揰傪墇偊傞傛偆偵側傝傑偟偨丅偨偩丄婥徾嬈柋巟墖僙儞僞乕偺夝摎偵偼摎偊偟偐婰嵹偝傟偰偄側偄偨傔丄夝愢偼屄恖偑塣塩偟偰偄傞乽傔偞偰傫乿偲偄偆僒僀僩傪嶲峫偵偟傑偟偨丅幚媄帋尡偼婰弎偑儊僀儞偱偁傝丄偨偩夝摎傪埫婰偡傞偺偱偼側偔丄側偤偦偺婰弎偵側傞偺偐傪棟夝偡傞昁梫偑偁傝傑偟偨丅條乆側帠椺傪夝偄偰偄偭偨偙偲偱丄栤戣偵傛偭偰偳偆偄偆僉乕儚乕僪傪梡偄傟偽傛偄偺偐偑尒偊傞傛偆偵側傝傑偟偨丅
嶲峫恾彂丗婥徾梊曬巑娙扨崌奿僥僉僗僩亙幚媄曇亜
俇丏妛壢偺暅廗傪偡傞乮俉寧拞弡乣乯
丂帋尡摉擔偺2廡娫慜偔傜偄偐傜妛壢偺夁嫀栤傪悢擭暘夝偒傑偟偨丅杮摉偼侾侽擭暘偔傜偄夝偒偨偐偭偨偺偱偡偑丄偙偺傑傑幚媄偵廳揰傪抲偗偽堦敪崌奿偱偒傞偲峫偊丄夁嫀栤偲帡偨栤戣偑懡偔弌戣偝傟傞朄婯暘栰傪拞怱偵夝偄偰丄偦偺懠偼寉偔怗傟傞掱搙偵偲偳傔傑偟偨丅
俈丏帋尡摉擔
丂帋尡夛応偼惉忛戝妛偱偟偨丄嵟婑傝墂偐傜偦偙偦偙曕偒傑偡偑丄晹壆偲堉巕偑偒傟偄側偺偱丄旕忢偵夣揔偵庴尡偱偒傑偟偨丅幚媄帋尡偱惙戝側儈僗傪廳偹偰棊偪崬傫偩偺偱丄婣傝偵媑徦帥偱旤枴偟偄傕偺傪怘傋偰儕僼儗僢僔儏偟傑偟偨丅乽媑徦帥偝偲偆乿偺娵儊儞僠傪攦偭偰丄堜偺摢岞墍偺儀儞僠偵嵗偭偰怘傋傞偲寵側偙偲偼戝掞朰傟傜傟傑偡丅旤枴偟偄僷儞壆偝傫傕懡偄偺偱丄偤傂梊曬巑帋尡偺屻偼媑徦帥偱梀傫偱婣偭偰偔偩偝偄丅
亂帺屓嵦揰亃
妛壢堦斒侾係丂丂妛壢愱栧侾俁丂丂幚媄嘆俈俆亇俁丂丂幚媄嘇俈俆亇係
亂戞俆係夞儃乕僟乕儔僀儞亃
妛壢堦斒侾侾丂丂妛壢愱栧侾侾丂丂幚媄丂俈侽
傆傝偐偊偭偰
梊曬巑帋尡偵崌奿偡傞偨傔偵戝帠側偺偼丄乽夝偄偨栤戣偺僷僞乕儞悢乿偩偲姶偠傑偟偨丅帋尡偱偼慡暘栰偐傜栐梾揑偵弌戣偝傟丄摨偠栤戣偼弌戣偝傟偢丄媄弍傕嵟怴偺傕偺偵峏怴偝傟偰偄偒傑偡丅偙偺傛偆側帋尡偵偍偄偰偼丄摨偠夁嫀栤傪孞傝曉偟夝偔偙偲偺堄枴偑敄偔(摿偵幚媄帋尡)丄條乆側栤戣傪夝偔傎偆偑摼揰偵偮側偑傞偲巚偄傑偡丅摿偵丄妛壢偼條乆側抦幆偺僀儞僾僢僩丄幚媄偼條乆側帠椺偺傾僂僩僾僢僩偵廳揰傪抲偔偲岠棪揑偵椡傪偮偗傜傟傞偲巚偄傑偡丅
|
2020擭11寧UP
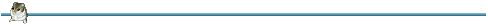
 偁偐偓傫曇丂2019擭搤崌奿 偁偐偓傫曇丂2019擭搤崌奿
|
偒偭偐偗
戝妛侾擭惗偺帪偵丄昅曐愭惗偺乽婥徾妛擖栧乿偲偄偆庼嬈傪庴偗偰丄婥徾偵嫽枴傪帩偪巒傔傑偟偨丅戝妛俁擭惗偱昅曐愭惗偺尋媶幒偵擖傜偣偰捀偒丄愭惗偐傜梊曬巑傪栚巜偟偰傒偨傜偲尵偭偰捀偄偨偙偲偱丄梊曬巑偵嫽枴傪帩偭偨偺偑巒傑傝偱偡丅奜晹偐傜棃偰壓偝傞榓揷偝傫偑梊曬巑崌奿偺偨傔偺庼嬈傪偟偰壓偝傞偙偲偵側偭偰偐傜丄杮婥偱梊曬巑傪栚巜偡傛偆偵側傝傑偟偨丅
摴偺傝
俀侽侾俈擭俈寧丂帋尡曌嫮奐巒
俀侽侾俈擭俉寧丂庴尡乮晄崌奿乯
俀侽侾俉擭侾寧丂庴尡乮晄崌奿乯
俀侽侾俉擭俉寧丂庴尡乮妛壢愱栧崌奿乯
俀侽侾俋擭侾寧丂庴尡乮妛壢堦斒丒幚媄崌奿乯
俀侽侾俋擭俁寧丂婥徾梊曬巑丂帒奿庢摼
侾丏帺暘偱嶲峫彂傪攦偆乮妛晹俁擭丂弔乯
丂傎偲傫偳婥徾偺抦幆偑側偐偭偨偺偱丄杮壆偝傫偵峴偒丄帺暘偑撉彂偺傛偆偵撉傔偦偆側嶲峫彂傪攦偄傑偟偨丅弶傔偵傢偐傝傗偡偔嫽枴偑桸偔杮乮帋尡偵岦偗偺杮偱偼側偐偭偨偱偡偑乯傪慖傫偩偺偼椙偐偭偨偱偡丅偔偠偗傞偙偲偑側偐偭偨偺偱丅
俀丏傠偔偵曌嫮偣偢偵帋尡偵岦偐偆乮妛晹俁擭丂壞丒搤乯
丂婥徾梊曬巑偺帒奿傪庢傝偨偄偲巚偄側偑傜傕丄侾恖偱嶲峫彂偵岦偐偭偰曌嫮偡傞傑偱偺儌僠儀乕僔儑儞偼側偔丄偲傝偁偊偢帋尡偩偗庴偗偰偄傑偟偨丅帋尡偺侾廡娫慜偐傜丄傕偟偐偟偨傜庴偐傞偐傕偟傟側偄偲巚偭偰埆偁偑偒偼偟傑偟偨偑乮徫乯
偳偆偡傟偽椙偄偺偐柾嶕偟偰偄偨帪婜偱傕偁傝丄侾恖偱婎慴抦幆傪擖傟偰偄偔偺偼擄偟偄側偲姶偠偰偄傑偟偨丅偙偺帪婜偵偼梊曬巑偺梊旛峑偺愢柧夛偵傕峴偒傑偟偨偑丄妛嬈偲偺椉棫偑擄偟偦偆偩偭偨偺偲丄巚偭偨傛傝庼嬈椏崅偔丄抐擮偟傑偟偨丅
俁丏拠娫偑偱偒傞乮妛晹係擭丂弔乯
丂尋媶幒偱婥徾梊曬巑傪栚巜偡拠娫偑偱偒傑偟偨丅拠娫偺巋寖傪庴偗偰丄帋尡懳嶔偺嶲峫彂乮偐傫偨傫崌奿僥僉僗僩乯傪偟偭偐傝撉傒巒傔傑偟偨丅廇怑妶摦偺帪婜偱傕偁偭偨偺偱丄堏摦偺揹幵偱奐偄偰戝帠偦偆側偲偙傠傪儅乕僇乕偱堷偔偲偄偆偺傪傗偭偰偄傑偟偨丅
係丏儅僢僗儖摴応偵嶲壛両乮妛晹係擭丂壞乯
丂奜晹偐傜榓揷偝傫偑婥徾梊曬巑懳嶔偺庼嬈乮偦偺柤傕儅僢僗儖摴応乯傪寧侾夞奐偄偰壓偝偭偰偄偨偺偱丄嶲壛偟巒傔傑偟偨丅儅僢僗儖摴応偼弔偐傜巒傑偭偰偄偰丄抶傟傪庢偭偰偄偨偺偱嵟弶偼偪傫傉傫偐傫傉傫偱偟偨乮徫乯偨偩妎偊傞偺偱偼側偔丄恖偵愢柧偱偒傞偔傜偄崻嫆傪棟夝偟側偑傜偺曌嫮偟偰偄偔偙偲傪嫵偊偰捀偒丄帺暘偱偺曌嫮朄曽朄偑曄傢傝傑偟偨丅
俆.杮婥偵側傞両夁嫀栤傕彊乆偵夝偒巒傔傞乮妛晹係擭丂侾侽寧乣乯
丂傗偭偲杮婥偵側傝傑偟偨丅偙偙偐傜幚媄偺曌嫮傪巒傔傑偟偨丅嶲峫彂偱抦幆傪僀儞僾僢僩丄夁嫀栤偱傾僂僩僾僢僩丄偱偒側偐偭偨偲偙傠傪嶲峫彂偱僀儞僾僢僩偺孞傝曉偟偺擔乆偱偟偨丅帪娫偑側偐偭偨偺偱丄夁嫀栤偼侾侽擭暘偩偗傗傝丄偱偒側偐偭偨偲偙傠偼俀夞栚傪傗傞傛偆偵偟傑偟偨丅
俇丏奜晹偺岞奐島嵗傪庴島乮妛晹係擭丂搤乯
丂奜晹偺岞奐島嵗傪庴島偟傑偟偨丅幚媄偼堦恖偱曌嫮偡傞偺偼擄偟偄偲巚偄丄俀夞嶲壛偟傑偟偨丅偦偺岞奐島嵗偱偼丄幚媄帋尡傪庴偗傞偵偁偨偭偰丄偳偆傗偭偰峫偊偰丄壗傪崻嫆偵丄偳傫側摎偊曽傪偡傞偺偐側偳丄夝偒曽傪嫵偊偰傕傜偄傑偟偨丅堦搙夝偒曽傪廗偆偲偙傟偐傜偺曌嫮曽恓偑傢偐傞偺偱偲偰傕傛偐偭偨偱偡丅
俈丏嵟屻偺媗傔
丂堦斒婥徾妛偺嵶偐偄偲偙傠傑偱丄曌嫮偟捈偟傑偟偨丅屻偼丄偱偒側偐偭偨偲偙傠傪傕偆堦搙夝偒捈偟丄帋尡偵椪傒傑偟偨両
傆傝偐偊偭偰
儌僠儀乕僔儑儞偺堐帩偑偲偰傕擄偟偐偭偨偱偡丅傂偲傝偱曌嫮偡傞偙偲偑懡偄偺偱丄偦偺拞偱傕丄岞奐島嵗傗妛峑偺庼嬈丄YouTube傪忋庤偔棙梡偟偰丄恖偐傜嫵傢傞婡夛傪庢傝擖傟偰偄偔偙偲偑戝愗偩偲姶偠傑偟偨丅偱傕丄壗傛傝傕戝愗側偺偼栚昗傪帩偮拠娫偲弌夛偆偙偲丅偦傟偼婥徾梊曬巑偩偗偲偼尷傝傑偣傫丅巹偼尋媶幒偵棃偰曌嫮偡傞偙偲偱丄尋媶傗懖榑偵岦偐偭偰婃挘偭偰偄傞拠娫偲偲傕偵曌嫮偟丄儌僠儀乕僔儑儞傪曐偭偰偄傑偟偨丅堦恖偩偗偱偼婃挘傟側偄偙偲傕丄廃傝偺巋寖傪庴偗傞偙偲偱椡傪傕傜偄傑偟偨丅尋媶幒偺傒側偝傫丄偁傝偑偲偆丅
偱偒傞傛偆偵側傟偽丄帋尡曌嫮傕妝偟偄偱偡偑丄偦傟傑偱偺抦幆偺僀儞僾僢僩偼偒偮偐偭偨偱偡丅偦偙傪妝偟傒側偑傜偱偒傟偽丄崌奿偼嬤偯偄偰偔傞偺偱偼偲巚偄傑偡丅
|
2019擭3寧UP
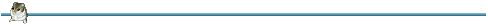
2014擭10寧UP
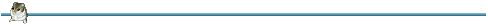
2013擭2寧UP
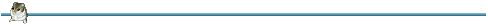
2011擭8寧UP